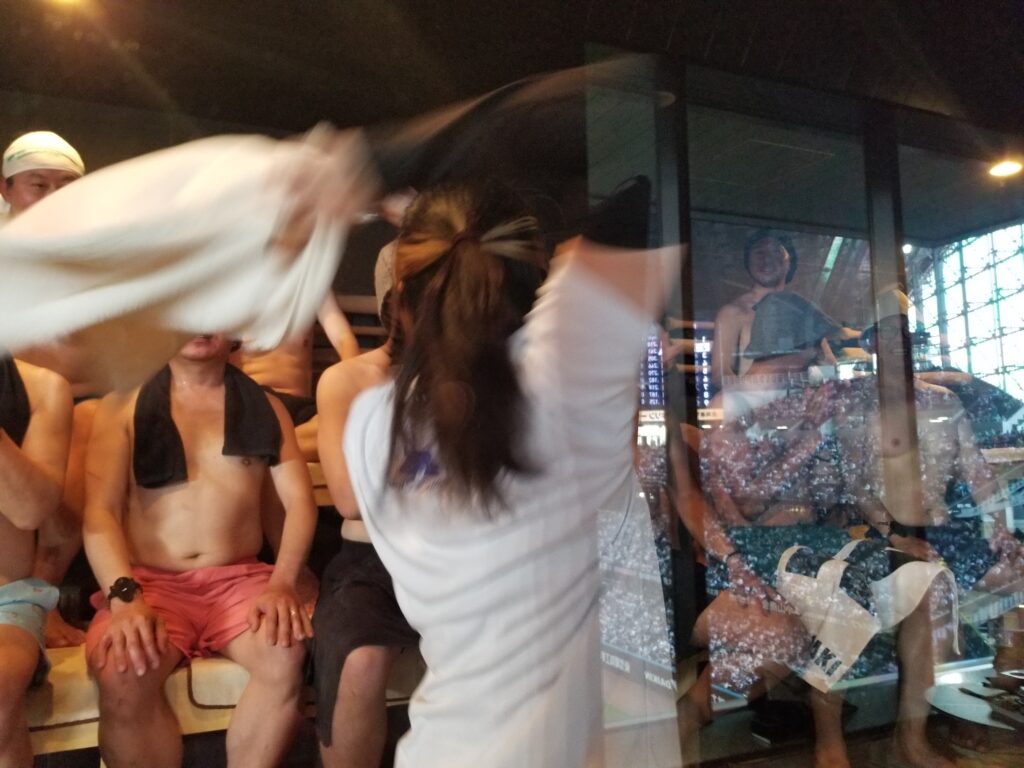施設の“価格印象”は、お客様の満足度や再来店意欲に直結します。そしてその入口にあるのが、実は「自販機の価格」なのではないかと、改めて考えさせられる出来事がありました。
先日、ご支援先のある温浴施設にて、会議の合間に一息つこうと、エントランス近くにあるお客様用の自販機に向かいました。目にとまったのはペットボトルのコーヒー。微糖が170円、無糖は180円。
「あれ?無糖の方が高い?」
そう思いながら、他の商品にも目を移すと、お茶や水もコンビニより高めの設定。「えっ、高っ」と思わず声が出そうになるような価格帯でした。
施設側に確認したところ、「自販機の価格はメーカー任せ」とのこと。
そのとき、ふと頭に浮かんだのが、到着時に目にしたもうひとつの自販機のことでした。
建物の外階段を上がる手前、道路沿いに設置されていた1台の自販機。通用口に近く、業務用のような雰囲気が漂っていたため、何気なく価格をちらっと見ていました。
ラインナップはほぼ同じなのに、スーパーマーケットプライスで明らかにこちらの方が安い。後から聞いたところ、それは従業員向けの自販機とのことでした。
以前はバックヤード内に設置されていたそうですが、現在はお客様の動線上からも見える場所にあり、誰でも購入できてしまう状態です。
もちろん、従業員用の福利厚生価格を設けること自体はまったく問題ありません。ただ、その価格差が視覚的に確認できてしまう環境にあると、「自分は高い値段を払わされているのでは?」という違和感につながりかねません。
これは、施設全体の信頼感や価格バランスを揺るがす、小さな綻びになり得ます。
とくに自販機は、喉を潤したいタイミングで真っ先に目に入るものであり、かつ、どこにでもあるため比較されやすい存在です。その“割高感”は体験全体の印象にも残りやすくなります。
それでいて、収益面ではそれほど大きなメリットがあるわけでもありません。フルオペレーション契約の場合、施設に入る手数料は売上の10〜20%程度が一般的です。180円で売れても、施設の取り分は十数円にとどまります。割高感を与えてまで得る収益としては、効率が良いとは言えません。
一方で、施設側が価格設定に関与できる仕入れ型の契約であれば…
注目の業界ニュース
【浴槽レス物件の拡大、コスパ・タイパ志向が後押し】
https://www.fnn.jp/articles/-/871205?display=full
物価高騰を背景に、浴槽を設けない“浴槽レス物件”が都市部を中心に人気を集めています。掃除の手間が省けることに加え、家賃や水道代を抑えられる点が、特に若年層の単身世帯に支持されているとのこと。
生活の近代化とともに自家風呂の普及率は95%を超えてきましたが、近年は逆の動きもあるようです。普段はシャワーで済ませ、じっくり入浴したい時に温浴施設を利用するというライフスタイルが広がっていくのかもしれません。