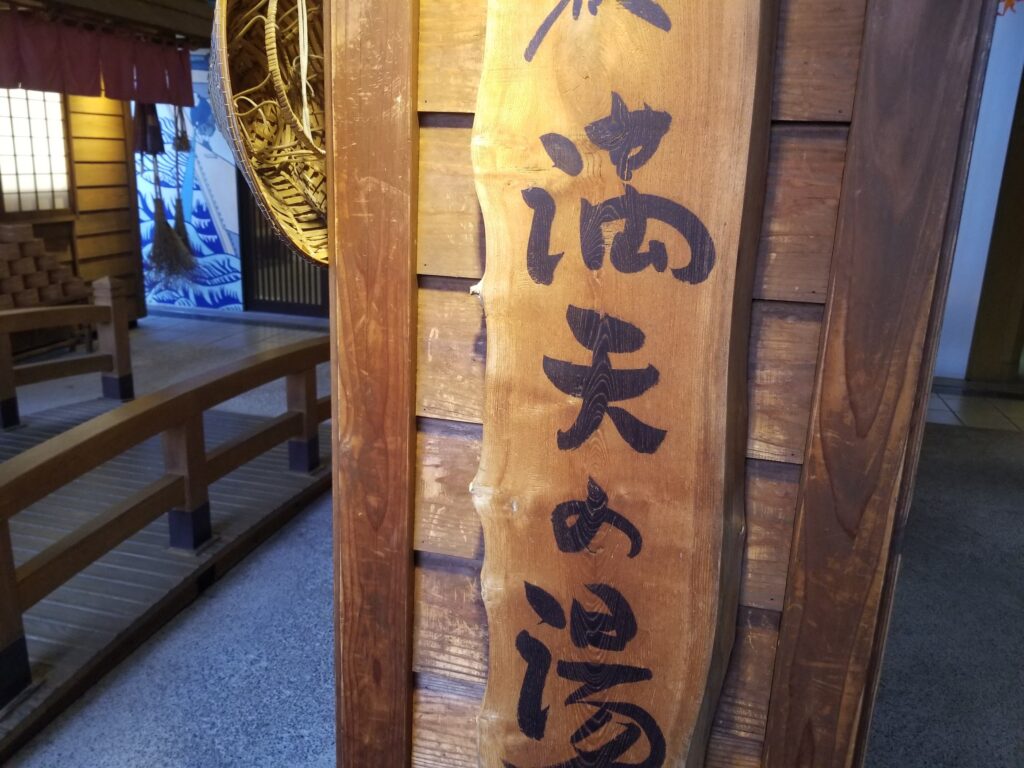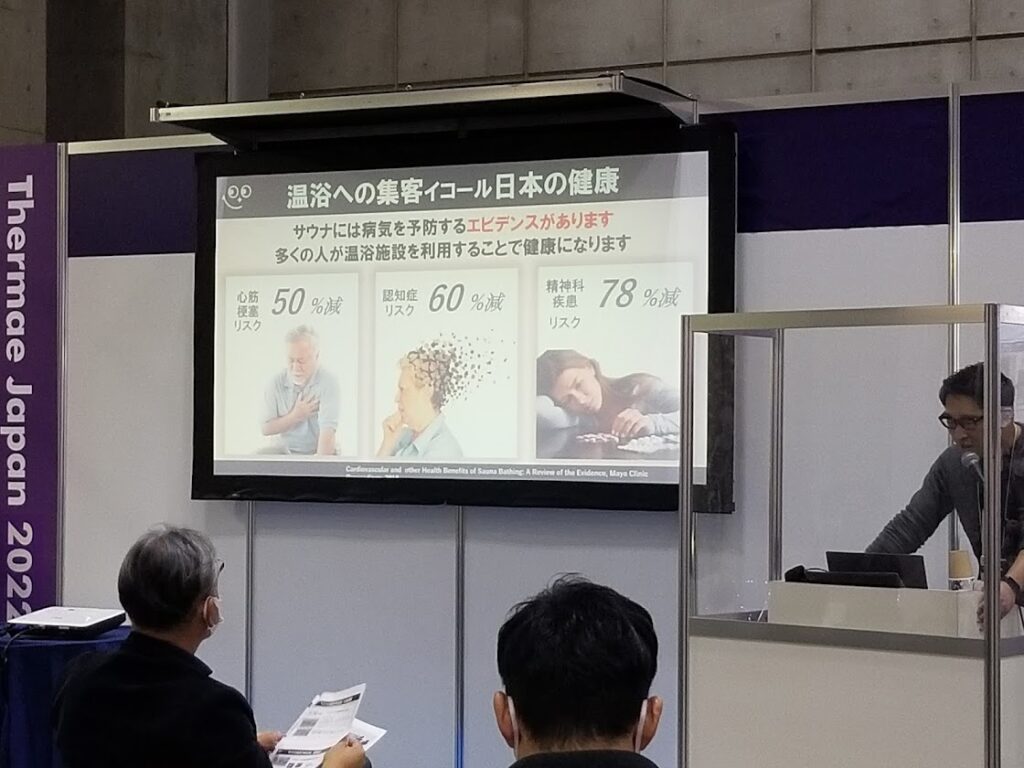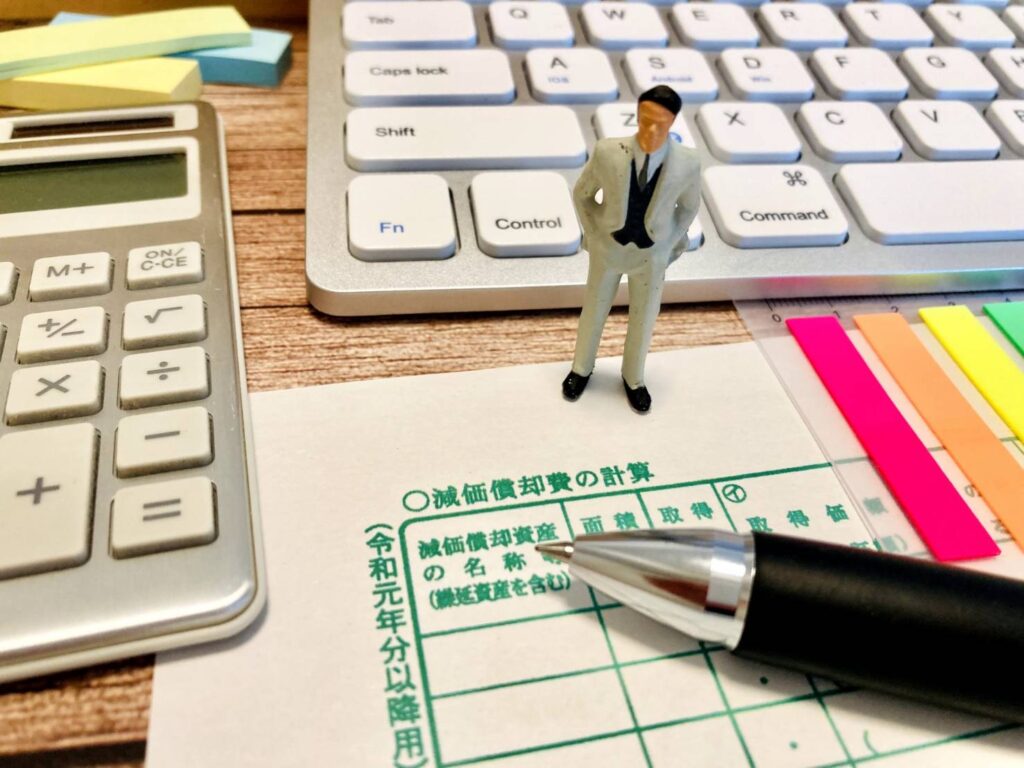
前回のメルマガ第2775号「温浴マーケットの行方」(2025年8月2日配信)で、
──考えてみれば、銭湯とその他公衆浴場を合わせた温浴施設数は全国に約2万件弱。各施設の平均寿命が約20年とすると、年間約1,000施設ずつが開業・廃業しながら新陳代謝を繰り返していることになります。
開業件数はその時の景況やマーケットトレンドに敏感に左右される傾向がありますが、それに比べると廃業件数は割とコンスタントに年間1,000施設前後で推移していますので、上記の新陳代謝理論は概ね現実と一致しているということが分かります。──
と、書いたのですが、この新陳代謝理論に基づけば、温浴施設は開業から平均約20年で閉館するということであり、その廃業時期をもっと後ろに遅らせることができれば、マーケットは拡大する可能性があるのでは?と考えました。
どこかで廃業する施設があって、その地域のマーケットに空白地帯ができることで新規開業が促されるという面もなくはなさそうですが、実際に新規開業案件をお手伝いしている限りでは、マーケットに空きができたからやろうといった話はほとんどなく、競合があろうがなかろうが、温浴ビジネスをやりたいからやる、ということが多いです。
つまり、廃業した施設の再生オープンというケースを除けば、純粋な新規開業件数は廃業件数にはあまり影響されていないと考えられます。新規開業のペースが一定であるとすれば、廃業時期を遅らせて、平均事業期間が20年から30年へと伸びていくことで施設数が増えるのではないか、という理屈です。
日本の出生数は1970年代の第二次ベビーブームをピークに以降は減り始めたにも関わらず、平均寿命が延びることで日本の人口が2008年まで増え続けていたのと同じことです。
温浴施設の平均寿命(事業期間)が伸びると考えたのは、いくつか思い当たる理由があるからです。
ひとつは…
注目の業界ニュース
【シニア旅行離れの背景に「デジタル化の壁」と混雑ストレス】
https://dot.asahi.com/articles/-/262005?page=1
2024年の国内旅行市場は過去最高の約25.2兆円を記録する一方、60代以上の旅行参加率はコロナ前から大幅に低下。特に70代では宿泊旅行経験率が約13ポイント減の37.8%、日帰り旅行も31.2%に落ち込みました。要因にはDX化への対応困難や訪日客増による混雑があり、旅行意欲はあるものの「使いづらさ」や「疲れやすさ」が障壁に。
シニアにも配慮した予約導線やデジタル操作のサポート体制の整備が、今後のシニア層の集客力強化の鍵となりそうです。