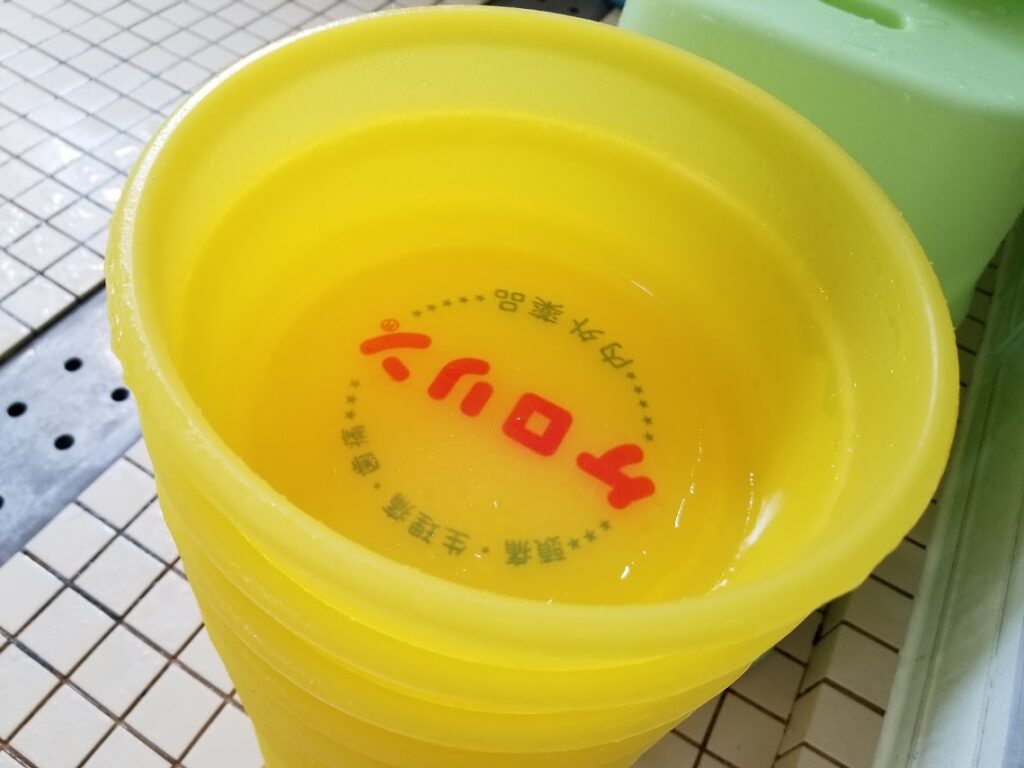先日、ある施設の研修で「歴史の授業」を担当しました。
テーマは日本の温浴文化の歩み。古代の蒸し風呂から江戸の湯屋、戦後のレジャー施設、そして現代のサウナブームまで。
大学時代にサウナブームを卒論で研究していた自分にとっては、まさに腕が鳴る仕事でした。
講座後のアンケートで「施設の歴史と重ね合わせて聞けたのが良かった」という声をいただくことができ感無量でした。
そのとき改めて感じたのは、歴史を学ぶことの意義とは、過去の知識を増やすことではなく、自店の「今」を見つめ直し、次の一手を考えるための羅針盤を手に入れることだということです。
たとえば近代以前の日本の入浴文化には、大きく三つの流れがあります。
地域の人が集う「銭湯」、旅や慰安など非日常を目的とした「温泉」、そして心身の回復を目指す「湯治場」。
自店がこのどの流れを汲むのかを見つめ直すことは、戦略を考えるうえで大きなヒントになります。
銭湯のように「地域の日常」を支える施設なら、気軽に立ち寄れる価格設定や、住民同士が顔を合わせるイベントが重要です。
温泉型なら、非日常の体験を徹底的に磨き込み、滞在時間や空間演出で「ここに来る理由」をつくる。
湯治場の系譜を引くなら、健康や美容といった具体的な効果を体系化し、プログラムとして提供することが鍵になります。
このようにお客様に提供する価値の「軸」が定まると、施設の判断がぶれなくなり、スタッフの意識もそろいやすくなるはずです。
また、歴史を知ることは、そこにしかない…
注目の業界ニュース
【データセンターの廃熱を地域で再利用、温浴施設活用にも期待】
https://www.ntt-f.co.jp/news/2025/20251029-01.html
NTTファシリティーズは、AI時代に対応した「地方共生型高効率データセンターモデル」を考案。サーバーの廃熱を住宅やオフィス、ビニールハウス、温浴施設などへ供給し、地域全体でエネルギーを循環させる構想です。自然の風を使った冷却や新しい空調システムにより、従来比50%以上の省エネを目指すとのこと。
まだ構想段階ですが、実現すれば新しいエネルギー連携が広がり、温浴施設にも持続可能な運営モデルをもたらす可能性があります。