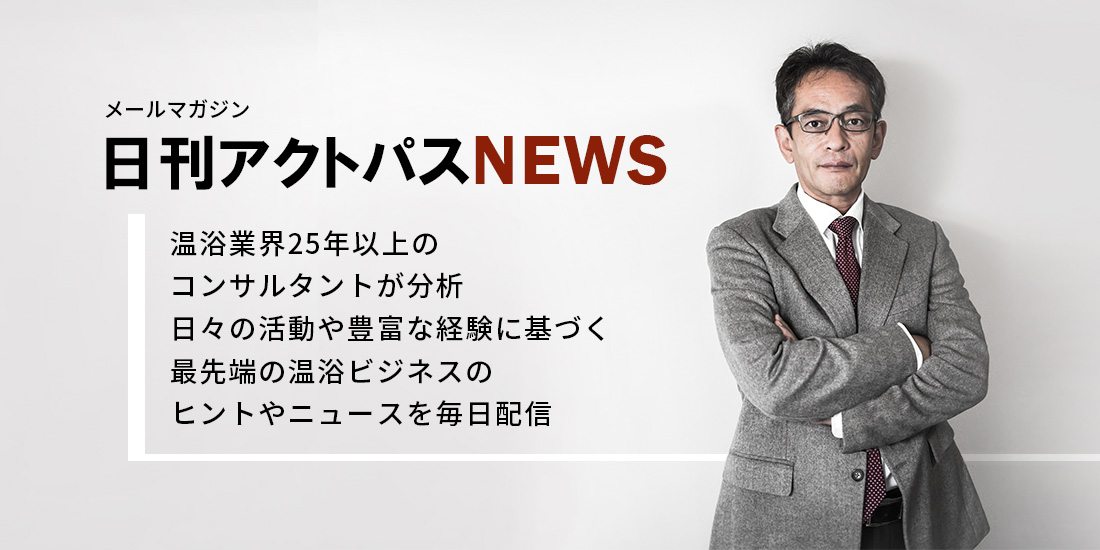
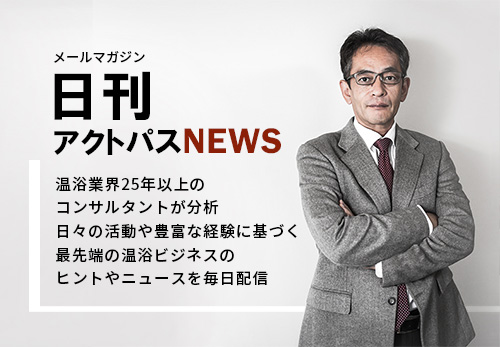
温浴業界の最新ヒントとニュースを提供する専門メールマガジン
★特にご購読をオススメしたい方★
- 温浴施設や大浴場を持つ施設を経営されている方
- 温浴施設の開業準備段階の方
- 温浴関連事業での起業を検討されている方
- サウナや銭湯の経営・運営に少しでもご興味がある方
- 温浴ファンとして業界や施設の裏側まで知り尽くしたい方
まずは1週間、ぜひお試しください!
【本メールマガジンの特徴】
-
温浴ビジネス特化のメールマガジン
唯一無二の温浴ビジネス特化型メールマガジン。
長年にわたる業界の革新への取り組みを通じ、新たなビジネスチャンスや次世代トレンドをいち早く伝えます。 -
多彩な執筆陣
25年以上の業界経験を持つ温浴コンサルタントの第一人者を中心に、バラエティ豊かな執筆陣が在籍。
経営戦略、マーケティング、デザイン、現場の声など、様々な視点から温浴ビジネスの課題に切り込み、実践的なノウハウを提供します。 -
業界情報を毎日更新
温浴業界のプロフェッショナルたちに役立つ情報を、毎日更新し提供しています。現場で直接活用可能なヒント、参考になる事例、明日への活力となるニュースを網羅。
2016年の創刊以来、日曜祝祭日および弊社の夏季・冬季休暇を除く毎日配信し、2400号以上を数えます(2024年5月現在)。
【過去バックナンバー抜粋】
◆どうなる?女性サウナー
軽い気持ちで申し込んだジートピア・ニューウイング・北欧の3施設合同レディースデーに当選し、せっかくなら同日に行われたかるまるレディースデーへの影響も確認すべく、バレンタインにひとり4店舗を巡ってきました。
ジートピアの店頭に、男性のお客様へ「本日レディースデーのためご利用いただけません」「グランドサウナサさん、個室サウナRe:さんをご利用ください」というメッセージがあったのがとても良いなと思いました。グランドサウナでは女性も購入できる物販を用意していたようですし、船橋の連帯感が素敵でした。
さて、3店舗のほうは完売、かるまるは若干の余裕があったようです。そして、行っていませんが、SAUNASはすいていたようです。
これらの情報に加え、スケジュールや体調で来れなかった方などを考慮すると、関東の本気度の高い女子サウナーは約500名と試算しました。
(もちろん、遠方から新幹線や飛行機でやってこられた方もお見掛けしましたが…。)
さて、今日の参加者の中で、あのカオスだった初回のかるまるレディースデーにいた人はどのくらいいるんだろう? 女性サウナーは本当に増えているのだろうか?
客層はなんとなく若返っているように思えますが、果たして本当なのか?
ということで、年齢はわかりませんが、参考までに各施設の今回のレディースデー1日でのサ活増をチェックしてみました。
※店舗名は私が回った順番です。
ジートピア 65件
ニューウイング 103件
北欧 87件
かるまる 64件
1泊2日分ですが、まず、一気にこれだけサ活が増えるというのがレディースデーパワーです。
以前にも書きましたが、やはり、これが施設側にとっての大きなメリットのひとつと言えるのではないかと思います。
各店舗は通常営業をするだけでなく、当日限定のイベントなども実施されていました。
ジートピア
…ウィスキング&グループウィスキング・似顔絵
ニューウイング
…特別物販・ワークショップ
北欧
…特別物販・ゲストアウフグース
かるまる
…スタッフ&ゲストアウフグース
上記以外の店舗でも、レディースデーでは通常よりもサービスを強化してくださることが多く、それも人気に拍車をかけていると思われます。
かるまるなどは、入場1時間後に薪サウナが自動でついてきますし、レディースデーのほうが快適なのでは?と思ったりもします。
いずれにしても、レディースデーにはサ活を書きたくなる要素が満載なのです。
他にはない、特別な体験を提供するという視点は、メンズ施設に限らず、イベントを行う際の重要なポイントと言えるでしょう。
そして、上記のうち、各施設に初めて来店されたと思われる方の数は以下の通りです。
ジートピア 44件(68%)
ニューウイング 52件(50%)
北欧 56件(64%)
かるまる 27件(42%)
レディースデーの実施回数が少ないジートピアは新規が多く、サ活から女性リピーターに愛されていることが強く感じられるのがニューウイング(そして宿泊者のサ活が多い)、いつかいってみたい、憧れだったとメンズからも言われているのが北欧、毎月レディースデーを行っているかるまるは安定的に利用されている印象を受けました。
サ活を書くのは一部の方だけですが、それでも新規の方がこれだけいるということは、いまだ女性マーケットは広がっているという確信を持ちました。
先日、湯らっくすの西生社長が、Twitterで「2017年の男性サウナで多発していた事故が今女性サウナで起きてる。」と書かれていました。
「女性サウナ愛好家の最近の増加っぷりに驚くと共に歓迎しております。」「まさか女性が増えてくるとは思ってもいなかったので嬉しいの一言です。」
https://twitter.com/yulax_kumamoto/status/1622138451960406016
2017年と言えば、サウナイキタイが開設された年で、まだ今のようなブームが来る前のこと。サ道のドラマ化と、想定外だったコロナ禍を経て、5年後のいま、女性が増えてきているということなのです。
大人気施設のこの傾向は、おそらく全国に波及していくものと思います。
その時に、女性を万全の態勢で受け入れる準備はできていますでしょうか?
新型コロナの5類移行が見えてきた今、いよいよ本格的に女性客が戻ってくることが期待されます。
いち早くその流れをキャッチし、現場の態勢を見直し、強化して、チャンスの前髪を掴んでいきましょう!
(望月啓子)
◆サウナマーケット分析
夢のお告げというわけではないのですが、今朝起きた時にふと思いついて、サウナイキタイから得られるデータを分析してみました。
https://aqutpas.co.jp/saunamarketbunseki/
どんな分析を思いついたのかと言うと、サウナイキタイに出てくる「サ活」と「イキタイ」の数をエリアの人口データと重ねてみると、どのような違いが現れてくるのか?ということです。
サウナマーケット動向をよくご存じない方のために解説しておきますと、サウナの情報検索サイト「サウナイキタイ」では、ユーザーが実際にサウナ施設を訪問した際の感想などをコメントすることを「サ活」と言い、実際に訪問しているかどうかに関わらず行ってみたいと思っている施設ページのボタンをクリックすることを「イキタイ」と言っています。
https://sauna-ikitai.com/
サウナイキタイに掲載されている中でも高評価の施設は、どんどん「サ活」や「イキタイ」が増えて行くという仕組みです。ユーザーの主観による評点を排除し、定量的なデータを重視しているのが「サウナイキタイ」という人気サイトの特徴のひとつとなっています。
まず、日本全国の総人口は125,502千人。サウナイキタイの登録サウナ施設数は日本全国で10,043施設、現時点のサ活数は2,093,693(2022年6月14日現在)、これが基本データです。
残念ながらイキタイ数は個々の施設のみが分かるようになっており、全国や都道府県での集計はされていません。
全国すべての地域を調べるのは大変ですので、まずはサウナマーケットの動きが活発と言われる北海道、東京都、山梨県、鳥取県、佐賀県を比較してみました。
エリアの人口を施設数で割った1施設あたり支持人口を見ると、全国平均12,496人/施設に対して、東京都は上回っています。これは地域人口に対してまだ施設数が不足傾向であるということを意味します。
逆に東京都以外はすべて全国平均を下回っていますので、サウナ施設数としては充実したエリアであり、施設同士の競争が厳しいとも言えるでしょう。特に山梨県は全国の3倍以上となっています。
1施設あたりサ活数を比べると、全国平均208件に対して、東京都は3.7倍の780件となっています。東京都以外の地域では全国平均を下回っているというのは予想外でした。
人口1,000人に対してどのくらいサ活が書かれているかという指標では、全国平均16.7サ活に対して、これも東京都が突出しており、47.7サ活。全国平均の2.9倍の水準です。北海道と山梨県も全国平均を上回っていますが、鳥取県、佐賀県は下回っています。
この1,000人あたりサ活数という指標は、その地域の実際のサウナマーケットの活動量ですので、この指標が小さいということは、地域内のサウナマーケットの掘り起こしにまだまだ可能性があるというとですし、地域外からの誘引もしきれていないと言えます。東京都の水準とまではいかなくても、全国平均と並ぶレベルを目標にするとしたら、鳥取県で3倍、佐賀県なら2倍に伸びる可能性がありそうです。
[地域の人口1,000人あたりサ活数÷全国の人口1,000人あたりサ活数]を計算し、その値が1.0以上なら流入都市、1.0以下なら流出都市。これをサウナ吸引力指数と言います。(笑)
このような分析は、統計データが一般公開されている都道府県レベルだけでなく、特定の地点でも行うことができます。
人口は30分圏人口を使い、エリア内のサウナ施設数、そのサ活数やイキタイ数をカウントすれば、全国平均や都道府県平均との比較ができ、そのエリアのサウナマーケット開拓余地や出店余力などを計ることができるのです。
全国や都道府県のイキタイ数がカウントできるともっと面白くなるのですが…
いずれにしても、弊社の今後のマーケット診断指標にも活かせそうです。
(望月 義尚)
◆繁盛店の共通項
昨日は全国でも有数の温浴激戦区で、地域のトップ3の繁盛店を視察してきました。
立地条件や施設規模はそれぞれ違うのですが、平日の昼間だというのに、どの施設も駐車場を見ただけでお客さまがかなり来ていることがうかがえました。
それぞれの施設の個性を楽しませてもらったのですが、これら繁盛店にはいくつかの共通項がある、ということに気づきましたので、今回はそれを整理してみたいと思います。
(1)コロナ対策緩め
入口での消毒や検温といった一般的な感染防止対策は実施されていますが、館内を見渡すと全体的な感染防止対策は緩めと言えます。
椅子があるのに座る場所を制限するような強制ディスタンスなどが少なく、どちらかというと館内ではコロナ禍であることを忘れてしまいそうな雰囲気です。
感染不安心理はまだ人それぞれですが、本当に強い不安を持っている人はそもそも温浴施設に来ていないでしょうから、あまり過剰な対策はかえって来館されている人の不安心理を煽ることにつながってしまいかねません。
安心安全な環境の提供が大切とはいえ、コロナ対策に関してはやり過ぎないようなバランス感覚が必要です。
(2)オンリーワンの挑戦
3つの施設それぞれで、「他では見たことがないような取り組み」を見つけました。こうした取り組みは、自分たちで考え抜いてチャレンジしているということで、素晴らしいと思います。
昨日一番驚かされたのは「サウナマット自動洗浄棚」。ビート板と呼ばれる樹脂製のサウナマットを使用後に棚に戻すと、霧が吹き付けられて洗い流されるという仕組みです。
おそらくDIYで工夫したものと思いますが、共有のビート板は前の人が使用後に洗ったかどうか定かでないので、画期的なソリューションだと思いました。
オンリーワンの取り組みは、どれだけの成果が上がるのか、実際にやってみなければ分かりません。リスクや費用対効果ばかり考えていたら進めることはできません。
どうしたらもっとお客さまに喜んでもらえるのか、どうやって貢献するのかを常に考えているからこそ、リスクを突破できるのでしょう。
結果として、前例のないオンリーワンの取り組みは他店と比較することのできない強い差別化要素となり、口コミにもなりやすいので、常識的なことをやっているよりもむしろ費用対効果は高くなるのです。
(3)サウナマーケットをキャッチ
コロナ禍でも大きく市場拡大しているサウナマーケット。ここを逃さない手はないのですが、繁盛店はサウナファンの心理をキッチリ抑えています。
これさえやれば良いといったことではなく、ロウリュからオロポ、売店商品まで、様々な要素を取り入れることでサウナーウエルカムな施設であることがよく伝わってくるのです。
まさに「サウナブームの風に乗る」ですが、勉強熱心なだけでなく、施設側にサウナファンの心理をよく分かっているスタッフがいるんだろうな、ということを感じます。
(4)若い客層
平日昼間ですから、かつてであれば来館者は年配客と主婦が中心という時間帯ですが、館内には10代、20代の若い世代が目立ちました。
上記のサウナーウエルカムな取り組みもその一環ですが、館内Wi-Fiやコミックなど若い客層が楽しめるような要素が多くあり、その情報をうまくSNSなどのネット販促につなげているからこそ、集客ができているのでしょう。
この4つの要素が共通項でした。
競合には顧客を奪い合うという側面もありますが、有力な繁盛店がひしめくエリアでは、それぞれが顧客満足を追求して個性的なオンリーワンとなっていくことによって新たな市場が開拓され、市場が拡大するという現象が起きています。
人口×マーケットサイズ(一人当たり平均消費支出金額)から算出される理論的な市場規模よりもさらに多くの温浴施設が成立するようになるのです。
同業他社は敵ではなく、一緒に温浴市場拡大を目指す仲間であると考えた方がいい、ということをあらためて感じた視察でした。
(望月)
【著者プロフィール】
・望月義尚(もちづき よしひさ)
大手コンサルティング会社にて温浴事業の専門コンサルティングチームを創設。2006年に、より総合的な温浴事業プロデュースを目指して独立、株式会社アクトパス代表取締役に就任。これまで多くの温浴施設の開業やリニューアル、事業再生のプロデュースで実績をあげている。
・望月 啓子(もちづき けいこ)
ホテル・美容室・ネイルサロン・アロマテラピーサロン等、女性客対象のサービス業を中心に、業績アップ支援を行っている。NMAネイルサロン経営アカデミー主宰。2021年より株式会社アクトパス常務取締役に就任、女性温浴マーケットの拡大に取り組んでいる。
・渡部 卓也(わたなべ たくや)
音楽・映像・写真業界でイベント企画や販促を担当。アクトパスではWEBコンサルタントとしてMEOやSNS活用の最新ノウハウを追求している。デザインやビジュアル制作にも精通。
・原田 政也(はらだ まさや)
2022年度入社。熱烈温浴ファンを自称。学生時代に陸上競技で培われた体力と脚の速さを武器に、日本中の温浴施設とラーメン店を駆け巡る。特技は温浴施設での早脱ぎとラーメンの早食い。
【ご購読者様の声】
- 業界のみならず他業態までのトレンドのお話、マーケティング、サウナ設備、集客、財務のお話などなど非常に多岐にわたる内容を毎日配信いただけるのは、読み物として非常に有用だと思います。遠慮なくデメリットを言わせていただくと、、、自宅のおふろでのんびり読んでたら意外に切実な課題が記されていて全然癒されないことがたまにありますので要注意です。。。苦笑(株式会社 SAKURA PIRATES 代表取締役・株式会社温泉道場 社外取締役 酒寄学様)
- 私もサウナが大好きで日本中500施設近くのサウナ・温浴施設を周りましたが、アクトパスさんのメルマガからは毎回新たな知識・視点を必ずいただくことができます!これが毎日配信というのが本当にすごいです!毎日楽しみにしています!日替わりで書き手が変わるのも、飽きがこないポイントかと思います!(「サウナコレクション」運営責任者・株式会社HIDANE共同代表鈴木翔様)
- やみくもに足を突っ込めるほど甘い世界はなくそれは温浴業界も同じ。大資本パワーゲームはどの世界にもあり、ゆげ蔵が足先で温度を確認しながら業界に浸かっていくには情報が欠かせない。情報源のひとつにアクトパスのメルマガを選んでいます。知識をいかにコスパよく得るか。日刊で鮮度が良く、安い。(サウナゆげ蔵様)
- アクトパス望月社長の有料メルマガ登録してるので毎日見てますが、この回の趣旨もめちゃくちゃ勉強になったけど。まさか「元気玉」を比喩に出してくるとわ。ますます望月さん推せてくる(熱ッスル大野様)
- 大変勉強になるから購読しているアクトパス社のメルマガ。昨日と今日は代表の奥様がかるまるレディースデーに関してメルマガを書いている。めちゃくちゃ面白い。女性サウナーの熱すぎるサウナ愛を感じる。サウナ好きな方が運営している施設は良い。細部にまで魂が宿っている。All We Need Is Love.(サツマー様)
- 日刊アクトパスNEWS ためになる情報が毎日届き、夢が広がります♪︎ すごぉーい♪︎でも高いんですよね?安く安くお願いします、望月社長♪︎ 温浴のあれこれを1日あたりチロルチョコ2つ分という破格のお値段です! 安ぅーい♪︎ チョコ代を節約してダイエットにもなるし勉強にもなる、お得です♪︎(サウナサン足立社長)
- 役立つ情報、悩みの共有、明日への活力がここにあります!(K.M様)
- 一般的に出回らない独自の視点で参考になります。また、タイムリーに旬な話題を提供してくれるのがありがたいです。(O.Y様)
- 一サウナ好きとして、このメルマガを通して運営の仕事に関わるきっかけを頂いたと思っています。(N.R様)
- 「旬」と「本質」、どちらの情報も届く。毎日読めなくても、全てのメールに目を通しています。1万号目指して、これからも頑張ってください!(T.K様)
- 望月さんだけの時も良かったですが、今のチームで様々な視点からのニュースも非常に面白いです!(Y.N様)
- 情報の質と配信頻度が素晴らしいです。温浴ビジネスやその他関連領域に関しての解像度が高まります。(T.D様)
- 全く関係ない業界にいながらも、ビジネス視点としてスピード感と慎重さをもって投資を行い、既存のものを磨き上げお客様への価値を高め続ける、そのビジネスの基本を常に感じ取っています。首がもげるほどうなずきながら読んでいます。(K.R様)
【ご購読にあたっての注意事項】
- 支払い方法について: 当メールマガジンの購読料のお支払いは、クレジットカード決済、または年契約の場合のみ請求書払い(銀行振込)が可能です。法人クレジットカードをご利用いただくと、会社口座から直接の引き落としになり、立替の手間が省けます。
- 無料お試し期間に関して: 「購読申込」後、配信まで数日かかることがございます。申込から1週間は無料お試し期間とし、その後課金が開始されます。お試し期間内に継続購読を希望されない場合は、1週間以内にご連絡ください。
- キャンセルポリシー: お申込み後、購読をキャンセルするまで、料金の自動引落しが続きます。途中キャンセルは可能ですが、残り期間の返金精算は承ることができません。キャンセルをご希望の場合は、日刊アクトパスNEWS編集部(info2@aqutpas.co.jp)へご連絡ください。
- 著作権に関して: 本メールマガジンは非公開情報を前提に執筆しております。内容の引用や転載を希望される場合は、事前に弊社の承諾を得てください。
- メール設定のご案内: 携帯メールやフリーメールをご利用の際は、 @aqutpas.com からのメールが届くように事前設定をお願いします。受信文字数に制限があるメールアドレスの場合、全文が受信できない可能性がありますので、設定の確認が必要です。
- 購読申込とキャンセルの繰り返しについて: 購読申込とキャンセルが繰り返し行われる場合、ご購読をお断りすることもございます。
- 配信先の変更をご希望の場合は、次の情報を「日刊アクトパスNEWS」編集部までお知らせください。1.登録名 2.現在配信されているメールアドレス 3.新しいメールアドレス 「日刊アクトパスNEWS」編集部: info2@aqutpas.co.jp

